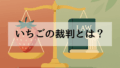「いちごは野菜?それとも果物?」この疑問、実は多くの人が一度は感じたことがあるのではないでしょうか。
見た目も味も果物そのもののいちごですが、農林水産省の分類によると、実は「野菜」に区分されているのです。
本記事では、なぜいちごが野菜とされるのか、その定義や科学的根拠、さらに日常生活で果物として扱われる理由まで、最新の情報をもとに徹底解説します。
この記事を読めば、家族や友人との会話で“食の雑学博士”になれること間違いなしです。
いちごは野菜?果物?結論から言うと「野菜」
農林水産省の定義による「野菜」と「果実類」の違い
まず、農林水産省では「果樹」として扱う作物について、「おおむね2年以上栽培する草本植物及び木本植物であって、果実を食用とするもの」と定義しています。
一方で、1年以内に収穫が終わる草本植物を原則とする「野菜」の分類があり、こちらには根菜類・葉茎菜類・果菜類・香辛野菜・そして「果実的野菜」という区分が設けられています。
“果実的野菜”とは、一般的には「果物のように食べられるが、生産統計上は野菜として扱われる作物」を指しています。
いちごが「野菜」に分類される理由
いちごがこのルールに当てはまる理由として、まず「草本性の植物」である点が挙げられます。
園芸学的に言えば、木になる“木本性”植物は果物扱いされることが多いですが、いちごは草本性であるため野菜とされるのです。
また、農林水産省が発表している統計調査では、いちごは「野菜(果実的野菜)」というカテゴリに含まれており、作付けや収穫の流れも「年間を通して苗を植えてから1年程度で収穫を終える」形態であることが理由となっています。
一般的に「果物」として扱われる背景
それでも、私たちの食生活でいちごは「果物」として認識されている場面が非常に多いです。
スイーツやデザートに使われること、甘くて生のまま食べられること、さらにスーパーでは果物コーナーに並ぶことも少なくありません。
こうした背景により、「いちご = 果物」という連想が根付いています。実際、消費者視点・販売視点の分類では「果物」とされるケースがあることも確認されています。
農林水産省の分類基準をわかりやすく解説
分類の基準は「栽培方法」と「利用目的」
まず、農林水産省が定める「野菜」と「果樹(果物)」の区分を確認すると、「概ね2年以上栽培する草本植物および木本植物で、果実を食用とするもの」を「果樹」として扱うと明記されています。
これに対して「野菜」は、生育期間が1年程度(1年以内に収穫される草本性植物)で、木化せず毎年栽培・収穫されるものが基本という考え方があります。
つまり分類の鍵となるのは「多年栽培か一年草か」「食用の部位が果実かどうか」「収穫・栽培方式」が大きな判定軸として機能しているわけです。
いちごが野菜に入る科学的・農業的根拠
次に、いちごが「野菜」に分類される具体的な根拠を見てみましょう。
いちごは一般に一年草または短期栽培の草本植物で、苗を植えてから比較的短期間(1年程度)で収穫されることが多いです。
これが「多年草・木本植物ではない」という点で、果樹とは異なります。実際に農林水産省の資料では、「メロン、いちご、スイカなどはいずれも一年生草本植物」であるため「野菜として取り扱う」と明記されています。
さらに、栽培・流通統計上でもこれらは「野菜(果実的野菜)」というカテゴリーに入れられており、農業・産業面からも「果実扱いではない」扱いがされているのです。
果物との比較で見える分類の曖昧さ
ただし、ここに「果物」と「野菜」の分類の曖昧さが見えてきます。
たとえば、消費者として「果物/フルーツ」という意識で捉えている作物が、農林水産省の統計分類では「野菜」に入っているケースがあるということです。
実際、「一年草の草本植物」「果実を食用とする」という植物学的観点とは別に、統計や行政運用上の「栽培期間」「木本か草本か」「産業上どの部門に入るか」という基準が重視されています。
さらに、たとえば「果実類」という言い方では、別の国や機関ではいちごやメロンを果物として扱っている例もあるため、日常の「果物=甘くてデザート的」というイメージと行政分類のギャップが出てくるのです。
植物学的に見る「いちご」はどんな植物?
いちごの構造と成長サイクル
いちご(Fragaria × ananassa)は、草本性の多年草または短期栽培型の植物であり、まず白い花を咲かせ、その後に赤く熟した可食部が形成されます。
日本における栽培では、苗の植え付けから収穫までは比較的短期間で行われることが一般的です。
花は5枚の花弁を持つことが多く、中央部分には多数の雌しべ(子房)が並んでおり、その外側を雄しべが取り囲む構造となっています。
成熟すると、赤くなった「実」に見える部分が我々の食用部であり、その上に小さなつぶつぶ(=痩果/そうか)が散らばっています。
「果実」ではなく「花托(かたく)」を食べている理由
植物学的に「果実(真果)」とは通常、花の子房が受精して発達したものを指します。
しかし、いちごの場合、我々が赤くて甘いと感じる可食部は、実は子房そのものではなく「花托(かたく)」と呼ばれる、花の基部である花床が肥大したものであるという点が特徴です。
表面の点々として見える黄色ishの「種に見えるもの」は、実際には“痩果”と呼ばれる小さな果実(子房が成長した構造)で、その中に本当の種子が含まれています。
こうした構造を「偽果(ぎか)」と呼び、いちごは典型的な偽果の例となっています。
他の似た分類例:メロン・スイカ・トマトとの比較
いちごと同様に、植物学的・農業的な分類がやや曖昧になりがちな作物として、 メロン や スイカ、さらには トマト があります。
例えばトマトは植物学的には果実でありながら、流通上は野菜として扱われることが多いです。
いちごも同様に“果物っぽい”見た目・味わいを持ちながら、栽培・分類の観点では果実類とは異なる扱いを受けるケースがあります。
こうした比較を通じて、いちごの分類がなぜ「野菜」に当てられるのか、その背景がより明確になります。
流通上・日常生活では「果物」とされる理由
青果市場での取り扱いと消費者のイメージ
実際の流通現場では、いちごは「果物(フルーツ)」として扱われることが多く、青果市場でも果実部門に出荷されたり、果物売場に並んだりしています。
たとえば、中卸・青果卸売市場でも「果実部が担当しています」と明記されており、消費者側から見た「果物」のイメージに合わせた流通体制となっていることが確認できます。
栄養・味覚の観点から見る「果物扱い」
いちごは甘みが強く、そのまま生で食べることが一般的なため、「デザート」「おやつ」「フルーツ」といった印象が定着しています。
こうした味覚体験や食べ方の観点から、多くの消費者が「果物」として認識しており、実際に野菜なのか果物なのかと考えるよりも、「甘くて美味しいフルーツ」というイメージで購入する場面が多いのです。
こうした消費者イメージを反映して、流通上も果物として扱われやすいという構図があります。
スイーツや加工品での扱われ方
さらに、いちごはケーキ・タルト・フルーツサンド・ジャムなど、スイーツや加工品において果物としての位置づけで多用されています。
こうした用途の広がりが、日常生活の中では「いちご=果物」という連想をさらに強める要因となっています。
実際、販売・マーケティング視点でも、いちごは“楽しむために食べる嗜好性の強い農産物”と位置づけられています。
まとめ|「いちごは野菜」だけど「果物のように親しまれている」
農林水産省の定義を正しく理解しよう
いちごは一見「果物」のイメージが強いですが、農林水産省の統計分類では「草本性の植物で、概ね1年以内に栽培・収穫される」という観点から「野菜」に分類されています。
このため、農業・統計上は「果実ではなく野菜(果実的野菜)」として扱われており、生産調査等でもそのように整理されています。
その一方で、日常生活や流通・消費の場面では、味・用途・イメージから「果物」として認識され、そうした意識ギャップが話題になることもあります。
分類の違いを知るともっと楽しい「食の知識」
分類の基準を知ることで、「いちご=果物」という常識がなぜ正確ではないのか、さらにその背景がどのようにして生まれたのかを理解できます。
植物学的な成り立ち、農業・流通の視点、消費者のイメージ。この三つが交錯することで、いちごは「野菜なのに果物のように親しまれている」という特異な存在として捉えることができます。
これを機会に、メロン・スイカ・トマトなど他の「見た目は果物っぽいけど分類上は…」という食材にも目を向けると、食べる楽しみが一層深まるでしょう。
ぜひ今日から、「いちごは野菜の仲間」という豆知識を友人や家族と共有して、食卓での会話をちょっと豊かにしてみてください。
出典情報:農林水産省「果樹とは」、農林水産省「野菜の区分について教えてください」、農林水産省『aff』特集「いちごの豆知識」、全農(JA)Q&A「いちごは野菜?それとも果物?」