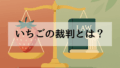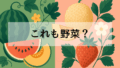私たちが日常的に食べている「いちご」。日本では果物として親しまれ、スイーツや贈答品の定番として定着しています。
しかし、アメリカでは驚くことに「野菜」として扱われていることをご存じでしょうか。これは単なる言葉の違いではなく、植物学的・法律的・文化的な要素が複雑に関係しています。
本記事では、アメリカでいちごが野菜とされる理由をUSDA(アメリカ農務省)の定義をもとに解説し、日本との食文化の違いを詳しく比較します。
さらに、両国のいちご産業や食の分類を通じて見えてくる“文化の背景”にも迫ります。
この記事を読むことで、普段何気なく食べている食材の「分類」に隠された奥深い世界を理解することができるでしょう。
いちごの分類は国によって違う?
日本では「果物」とされる理由
日本では、一般的にいちごは「果物」として認識され、その鮮やかな色味や甘味、贈答用途としての価値が高く評価されています。
例えば、輸出入資料によると「一般にイチゴは“果物”として扱われるが、農林水産省の分類上は“果実(果物)”ではなく“野菜”に含まれる“果実野菜”に分類される場合がある」と明記されています。
また、いちごの国内における生産・消費サイクルを見ても、冬から春にかけて収穫・流通がピークとなり、その期間にデコレーションケーキや贈答用途に使われることが多く、いちご=「果物」としてのイメージが定着しています。
このように、味・見た目・用途といった観点から「果物」という位置付けが自然に受け入れられています。
アメリカでは「野菜」とみなされる背景
一方、アメリカにおいて「いちご=野菜」とされるという説が語られることがありますが、実際には法的・行政的に「野菜」と明確に分類されているという公式な定義を示す資料は確認できません。
ただし、米国において食材をどのように「果物」「野菜」と捉えるかについては、法律(例えば輸入関税や関税分類)や慣習による判断が過去にあり、例えば Nix v. Hedden の判例では「トマトを果物ではなく野菜とみなす」という判断がなされています。
このような事例があるため、「イチゴも同様の線で“野菜”扱いになっているのではないか」という文脈で語られることがあります。
分類の違いが生まれる3つの視点(植物・法律・文化)
いちごの分類の違いがなぜ生じるのかを整理するために、植物学的視点、法律・行政的視点、文化・消費習慣の視点という三つの角度から考えてみましょう。
まず植物学的には、いちごは「バラ科イチゴ属」の多年草で、「果菜(果実のような野菜)」という捉え方も可能です。
実際、日本の資料では「果実ではなく“果実野菜”に分類される場合がある」と記されています。
次に法律・行政的に見ると、国や地域によって“果物”と“野菜”の定義・扱いが異なり、また輸入・関税・流通の枠組みの中で“果物”“野菜”の線引きがなされてきました。
最後に文化・消費習慣の観点では、例えば日本ではいちごが“高級果物”としてスイーツや贈答用に使われる一方、別の国ではもっと日常的な作物・野菜的な扱いを受ける、というような違いが存在します。
これら三つの視点が絡み合って、いちごの分類やイメージには国ごとにズレが生まれているわけです。
アメリカでいちごが“野菜扱い”される本当の理由
USDA(アメリカ農務省)の定義による分類基準
アメリカにおいて、United States Department of Agriculture(USDA)は栄養指導や流通ガイドラインの中で「果物(Fruit)」と「野菜(Vegetable)」をそれぞれの食のグループとして位置づけています。
例えば、USDAの「MyPlate」という食事指針では、果物と野菜が別々のグループとして示され、「Vegetable Group」には〈生・調理・凍結・缶詰・乾燥などの形式を問わず、野菜または100%野菜ジュース〉が含まれると記載されています。
一方、USDAの「Specialty Crop Definition」には「果物と野菜、木の実、乾燥果実、園芸および苗木作物」を含むと明記されており、農産物として果物・野菜双方が政策対象となっていることが分かります。
ただし、USDAが “いちご” を明確に「野菜扱い」と定義している公文書は確認できず、「野菜/果物」の分類は必ずしも植物学的な定義に基づいているわけではなく、食用慣習・流通・法律という観点が影響しています。
トマト・スイカ・ピーマンも「野菜」?法律上の線引きとは
アメリカでは、植物学的には種子を持ち、花に由来する “果実” に分類される食材でも、法律的・流通上の取り扱いにおいて「野菜」とされてきた例があります。
代表的なのが、19世紀に米国最高裁で扱われた Nix v. Hedden(1893年)で、同判例はトマトを「果物」ではなく「野菜」とするとの判断を示しました。
この判例では、関税法上 “vegetables” に課税義務があり “fruits” には免税枠があったため、貿易・関税目的での分類が重要視された点が背景にあります。
つまり「食卓で主菜とともに出る」「サラダや料理に使われる」という慣用的な使われ方が“野菜”と判断される基準となりました。
このような歴史的経緯があるため、いちごのような“果実的だが料理材料・加工材料・農作物”的な立ち位置の食材について、「野菜」的扱いが語られる土台が生まれています。
関税・流通・農業政策に影響する“野菜”の定義
分類が単なる呼び名の違いに留まらないのは、関税・流通・農業政策の観点から「野菜/果物」の線引きが実務的な影響を及ぼしてきたからです。
例えば、果物として扱われるか野菜として扱われるかによって、輸入関税率・国内補助金・流通チャネル・マーケティング表示などが変わる可能性があります。
上記のNix v. Hedden判例も「輸入時の課税対象」が争点でした。
また、USDAの“specialty crop(特定園芸作物)”制度では「果物と野菜」がまとめて支援対象になっており、農業政策上では両者を並列に扱うことで流通・栽培・補助金の枠組みを構築しています。
このように、アメリカでは「野菜」というカテゴリーのラベルが、栽培・収益・貿易の現場で重要な意味を持っており、そのため「いちごも野菜と見なされうる」という発想が文化的・制度的に生じているのです。
アメリカと日本の「いちご文化」を比較
日本では「スイーツ・贈答用」文化が中心
日本において、いちごは冬から春にかけての収穫期に「旬の果物」として広く親しまれています。
例えば、栃木県は「いちご王国」と呼ばれ、代表品種の「とちおとめ」が生まれた地域として知られています。
また、ハウス栽培や温室栽培によって、冬場から春先まで美味しいいちごが市場に出回る仕組みが整えられています。
こうした背景もあって、いちごは単に朝食で食べる果物という位置づけを超え、デコレーションケーキのトッピングや贈答用ギフトフルーツとしての価値を帯びています。
見た目の美しさ、甘さ、希少性などが重視され、「特別な果物」という印象が強く根付いています。
アメリカでは「日常食材・農作物」としての位置づけ
一方、アメリカではいちごは非常にポピュラーなベリー類の一つであり、家庭料理や日常のデザート素材として広く利用されています。
USDAのデータによると、アメリカ人一人当たりの新鮮ないちごの年間消費量は1980年代以降増加傾向にあり、2013年には1人あたり約7.9ポンド(約3.6キログラム)に達していました。
また流通量・生産量ともに大きく、農産としてのインフラも整備されているため、いちごが「手軽に買える果物・ベリー」という印象があります。
このように、アメリカではいちごが「日常の食材」として自然に生活に取り入れられており、その文化的背景には“果物=特別”という日本のイメージとは少し異なる価値観が存在します。
アメリカの家庭料理・デザートに見るいちごの使われ方
アメリカの家庭やレストランでは、いちごはそのままフレッシュで食べられるだけでなく、ヨーグルトやスムージー、サラダ、アイスクリーム、パイやタルトなどのデザート素材としても多用されます。
また、冷凍や加工品としての利用も一般的で、「ベリー類=健康志向の素材」というカテゴリーで語られることも増えています。
流通の機会や品種改良の進展によって年中手に入りやすくなったことで、いちご=“特別な日用”よりも“日常使い”の果実/ベリーという立ち位置が強まっています。
アメリカのいちご産業の現状と背景
主な生産地:カリフォルニア州が圧倒的シェア
アメリカにおいて、いちごの生産拠点として圧倒的な存在感を示すのが、カリフォルニア州です。
米国の新鮮ないちご生産量の約90 %がカリフォルニア州で賄われており、次いでフロリダ州が約8 %を占めています。
さらに、カリフォルニア州内の農地のごく一部(1 %程度の農地)でこの高いシェアを達成しているというデータも報告されています。
このように、いちご産業における地理的な偏りが大きく、特に生産・流通・マーケティングの基盤がカリフォルニア州に集中している点が特徴です。
栽培技術・流通・季節性の特徴
カリフォルニアのいちご産業では、近年においても栽培面積が拡大傾向にあり、2024年には農地面積が前年比5 %増で約42,320エーカー(約17,100ヘクタール)に達したとの報告があります。
また、技術面では新品種の導入や季節を拡張する栽培サイクルが進み、例えば4〜10月期の出荷増加も観察されています。
流通面では、収穫後の鮮度管理・輸送・パッケージングが徹底されており、例えば収穫から梱包・出荷までの効率化が進んでいます。
さらに、生産規模の大きさ・流通チャネルの確立により、いちごが「年間を通して」手に入りやすい食材となってきています。
健康志向といちご消費の拡大トレンド
アメリカでは健康志向の高まりに伴って、ベリー類、特にいちごが「スーパーフード」「抗酸化物質豊富な果実/ベリー」として注目されており、消費量も増加傾向にあります。
生産産業としての規模も巨大で、カリフォルニア州のいちご農業は直接的に約26.8億ドル(約数千億円規模)の経済波及効果を持つという推計もあります。
ただし、価格の変動・流通拡大・農地の増加などにより、いちご価格が抑えられ気味であるという指摘もあり、今後の品質維持/収益確保が課題として挙げられています。
国によって変わる“食の分類”という面白さ
日本の「農林水産省」とアメリカの「USDA」の違い
日本では 農林水産省(MAFF)が農産物の生産統計や流通分類を「野菜」「果物とナッツ」のように区分しており、例えば統計年鑑において「野菜」「果物とナッツ」という大分類が明記されています。
一方、アメリカでは United States Department of Agriculture(USDA)が「Fruits」「Vegetables」「Grains」「Protein Foods」「Dairy」という食事ガイドライン上の五大食品群を示しており、分類は栄養・食行動の観点からなされていることがわかります。
このように、同じ「野菜/果物」という概念でも、統計・農産物政策の枠組みと、栄養・食生活指針の枠組みでは扱いが異なるため、「どの観点で分類しているか」が極めて重要になってきます。
文化・法律・歴史が食の考え方を作る
食材の分類には植物学的な定義も関わりますが、それだけでは完結しません。
例えば植物学的には「種子を持つ/花から発生する実」は果物という定義がありますが、料理・流通・政策の観点では「調理して主菜の傍らに出る」「生で甘味が強くデザート用途」が果物・野菜を分ける基準となるケースがあります。
さらに、関税・貿易・農業補助金の歴史的背景を考えると、ある作物が「野菜」とされれば関税率や補助の対象が変わるといった制度的インセンティブも分類の背景として存在します。
これは先述の判例(Nix v. Hedden)などが示す通りです。
つまり、文化(食べる・贈る・日常か特別か)、法律/制度(関税・補助金・流通規制)、歴史(その地域の農業構造・輸出入関係)が相まって「これは果物?野菜?」という問いの答えは国によって変わるのです。
グローバルな視点で「いちご」を見直そう
こうした背景を踏まると、例えば “いちご” を眺めたときにも、単に「甘くて赤い果実」ではなく、その分類がどの基準でなされているかを意識することが新たな気づきを与えてくれます。
輸入実務や農産物政策、食卓での使われ方、スイーツに使われるかサラダに使われるか、そういった違いが「果物/野菜」というラベルを左右しているのです。
グローバル化が進む中で、作物の分類や流通、消費スタイルも世界的に交差しており、私たちが当たり前と思っている「いちご=果物」という価値観も別の国では異なる視点を持つことができます。
視点を少し変えて食材を眺めることで、食文化そのものを豊かに理解できるのではないでしょうか。
まとめ|いちごの“野菜扱い”から見えるアメリカの食文化
分類の違いは文化の違い
私たちが「いちご」と聞いて思い浮かべるイメージには、色鮮やかで甘く、スイーツや贈答品として映える“果物”という日本的な価値観があります。
しかし、国境を越えて視点を変えると、分類の仕方・扱い方・背景がまったく異なることに気づきます。
例えば、アメリカでは“果物/野菜”というラベルが単なる味覚や見た目だけではなく、法律・流通・農業政策と密接に結びついているため、同じ“いちご”でも分類の位置づけにズレが生まれています。
こうした分類の違いを通して見えるのは、食材そのものではなく、それを取り巻く文化・制度・歴史の違いなのです。
食の定義を知ることで世界が広がる
“いちご=果物”という固定観念を一歩引いてみると、そこには植物学・行政・消費文化という複数の視点が重なっていることが分かります。
そして、米国のように“いちごも野菜的な枠組みで捉えられ得る”という考え方に触れることで、私たちの食に対する理解は確実に広がります。
旅行先や輸入食材、世界中の市場で目にする“果物/野菜”の区分が、実は国によって変わりうると知るだけでも、食べ物の見方がより深まり、興味深い発見につながります。
次のステップとしてできること
この記事を読んだ後にぜひ試していただきたいのは、スーパーマーケットや海外旅行で“いちご”を手に取ったときに、「これは果物/野菜、どちらに分類されているのだろうか?」と少し意識してみることです。
あるいは、輸入食材や異文化圏のレシピで“いちご”がどのように扱われているかを調べるのも面白いでしょう。
そして、日本と海外で同じ食材を比べてみることで、食文化の違いや背後にある制度・歴史・産地の事情に思いを馳せるきっかけになれば幸いです。
- USDA MyPlate「Vegetable Group – One of the Five Food Groups」
- USDA公式ブログ「Back to Basics: All About MyPlate Food Groups」
- USDA AMS「Specialty Crop Definition(特定園芸作物の定義)」
- Justia「Nix v. Hedden, 149 U.S. 304 (1893)」
- USDA ERS「U.S. fresh strawberry production expands with newer varieties」
- USDA ERS「U.S. strawberry consumption continues to grow」
- California Strawberry Commission「Economic Impact」
- California Strawberry Commission「Economic Impact Report (2022)」PDF
- Terrain Ag「A Soft Season for California Strawberries」
- Colorado State University FSI「Strawberries – Food Source Information」
- JETRO「Highlighted Japanese Ingredient – Strawberries」
- Japanese Statistical Yearbook「Chapter 8: Agriculture(農業統計の区分)」
- National Agriculture in the Classroom「Fruit or Vegetable?」PDF